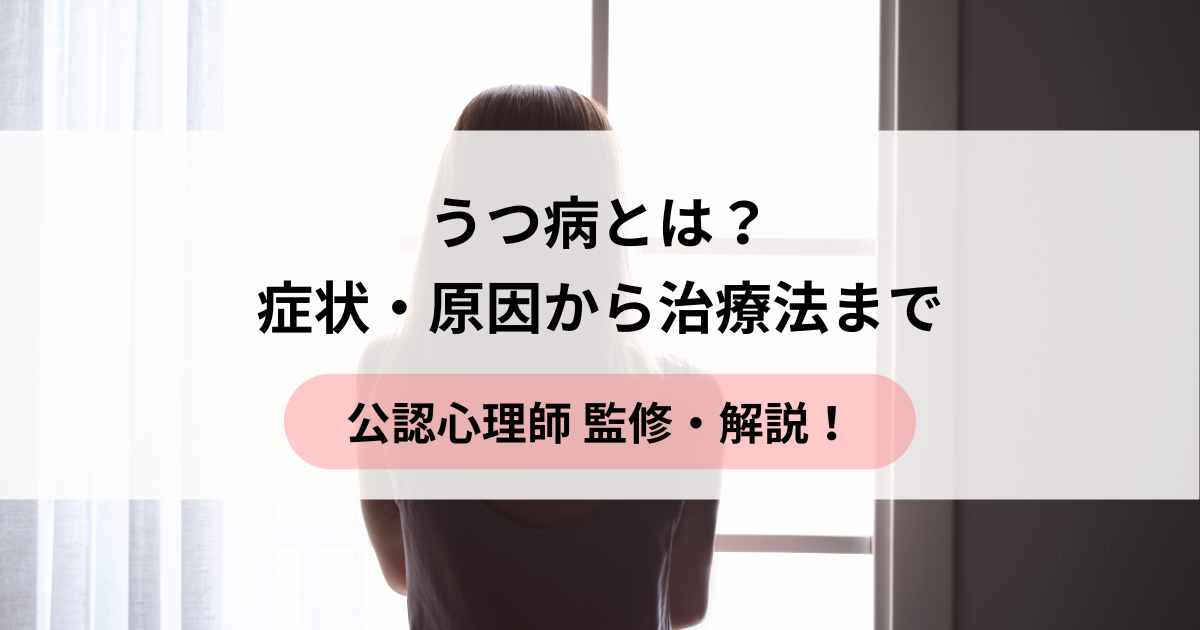現代のストレス社会の中で、うつ病は非常に身近な病気になっています。
「最近気分が落ち込み、なかなか抜け出せない」「やる気が出ない」といった症状でお悩みの方は少なくありません。今回は、うつ病について原因・症状から治療法まで解説していきます。
うつ病とは
そもそも、うつ病とはどういった状態を指すのでしょうか?うつ病の概要から見ていきましょう。
うつ病は、アメリカ精神医学会の診断基準DSM-5において「大うつ病性障害」と定義される気分障害の一つです。一日中気分が落ち込んでいる、何をしても楽しめないといった精神症状とともに、眠れない、食欲がない、疲れやすいなどの身体症状が現れ、日常生活に大きな支障が生じている状態を指します。
うつ病は「単極性うつ病」とも呼ばれ、うつ状態のみが現れるのが特徴です。
一方、うつ状態と躁状態(軽躁状態)を繰り返す「双極性障害(躁うつ病)」とは治療法が大きく異なるため、専門医による正確な診断が重要です。
有病率と性差
厚生労働科学研究費補助金による大規模疫学調査(対象者4,134名)によると、日本では約16人に1人(生涯有病率6.1%)がうつ病を経験しているという結果が出ています(2002-2006年)。
これ以降は同規模の疫学調査が行われておらず、この調査のデータが現在でも医学界の標準として使用されているのが実情です。
また、厚生労働省の患者調査では、気分障害の患者数は約100万人に上り、女性の方が男性よりも約1.6倍多いことが知られています。
世界保健機関(WHO)の報告では、うつ病は世界の疾病負荷の主要な原因の一つとされており、2030年には疾病負荷(病気や怪我が社会全体に与える影響の大きさを総合的に測る指標)の第1位になると予測されています。つまり、「最も多くの健康な人生を奪う病気になる」という意味です。これは死亡数だけでは見えない真の健康問題の深刻さを表している、といえるでしょう。

このデータから、うつ病が決して珍しい病気ではなく誰でもかかる可能性がある身近な疾患であることがわかります。
症状
DSM-5の診断基準に基づくうつ病の中核症状は以下の通りです。
精神症状
1. 抑うつ気分
- 一日中気分が沈み込んでいる
- 悲しみや絶望感が続く
- 理由もなく涙が出る
2. 興味・関心の著しい減退
- 以前楽しんでいた活動に興味がなくなる
- 趣味や娯楽を楽しめない
- 人との交流を避けるようになる
3. 精神運動の障害
- 思考や動作が遅くなる(精神運動制止)
- 逆に、落ち着きがなくイライラする(精神運動興奮)
4. 認知機能の低下
- 集中力や注意力の低下
- 決断力の低下
- 記憶力の問題
5. 罪悪感・無価値感
- 過度の罪悪感や自責の念
- 自分は価値のない人間だと感じる
- 自己評価の著しい低下
身体的な症状

うつ病では精神症状に加えて、以下のような身体症状も現れることが多くあります。
睡眠障害
- 入眠困難(寝つきが悪い)
- 中途覚醒(夜中に何度も目が覚める)
- 早朝覚醒(朝早く目が覚めて眠れない)
- 逆に過眠(一日中眠ってしまう)
食欲・体重の変化
- 食欲不振と体重減少(多くの場合)
- 逆に食欲増進と体重増加
身体的不調
- 慢性的な疲労感・倦怠感
- 頭痛や肩こり・身体の痛み
- 胃腸の不調
- めまいや動悸
- 性欲の低下
原因とメカニズム
現在の医学研究では、うつ病の発症に脳内神経伝達物質のバランス異常が関与していることが明らかになっています。
神経伝達物質は、脳内の細胞同士がやりとりするためのメッセンジャーの役割を果たしています。感情、思考、行動すべてをコントロールする重要な化学物質です。
主要な神経伝達物質
セロトニン
気分の安定、睡眠、食欲の調節に関与する。機能低下により抑うつ気分や不安が生じる
ノルアドレナリン
意欲、集中力、注意力に関与する。機能低下により無気力や集中困難が生じる
ドパミン
快感や意欲に関与する。機能低下により興味・関心の低下が生じる
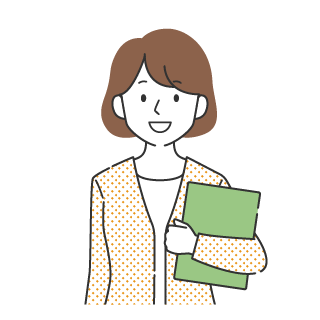
また、うつ病の患者さんでは
感情調節や判断力・意思決定を担う脳の前頭前野、海馬、扁桃体などの領域において構造的・機能的変化が認められることも報告されています。
リスク要因
うつ病の発症には、以下のような要因が複雑に関与しています。
1. 生物学的要因
- 遺伝的素因(うつ病の家族歴がある場合のリスクは2-3倍)
- ホルモンバランスの変化
- 他の身体疾患の影響
2. 心理社会的要因
- 性格特性(完璧主義、自己批判的など)
- ストレスフルなライフイベント
- 社会的サポートの不足
- 幼少期の体験(小児期逆境体験)
3. 環境要因
- 人間関係の問題
- 家庭・職場のストレス
- 経済的困難
- 季節性(冬季うつ病など)
治療法
うつ病の治療には休養・薬物療法・精神療法(心理療法)があります。
主な薬物療法(抗うつ薬)
SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)
- フルボキサミン、パロキセチン、セルトラリンなど
- セロトニンの濃度を高める
SNRI(セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬)
- ベンラファキシン、デュロキセチンなど
- セロトニンとノルアドレナリンの両方に作用する
NaSSA(ノルアドレナリン作動性・特異的セロトニン作動性抗うつ薬)
- ミルタザピンなど
神経伝達物質は、使われた後脳内で取り込まれるのが通常です。しかし取り込みを薬によって意図的に防ぐと、脳内での作用時間が長くなります。これを利用して、脳内の神経伝達物質のバランスを図るのがSSRIやSNRIです。一方、神経伝達物質の放出量自体を増やすのがNaSSAになります。
基本的にはこれらの薬物療法で脳内の神経伝達物質のバランスをコントロールし、その他各種身体症状に応じて薬剤が選択されることになることが多いでしょう(主治医と要相談)。
またうつ病の改善効果が乏しい場合には、上記以外の投薬が選択されることもあります。
精神療法・カウンセリング
精神療法も、投薬と並行して進められることの多い治療法になります。
認知行動療法(CBT)
- 症状に影響する思考パターンや行動の悪循環を修正する
- 中でも行動活性化療法と呼ばれる技法が最も効果的
- うつ病に対する効果は薬物療法と同等
- 再発予防効果が高い
対人関係療法(IPT)
- 人間関係やコミュニケーションのパターンに焦点を当てる
- 認知行動療法とほぼ同等の効果が確認されている
- 対人ストレスが中心のうつ病に強い効果を発揮する
その他の治療法
薬物療法や精神療法で十分な効果が得られない「治療抵抗性うつ病」に対する物理的治療法も存在します。
反復経頭蓋磁気刺激法(rTMS)
- 磁気刺激により脳の神経回路を調整・活性化する
- 薬物療法で効果不十分な場合に認定施設において適応される
- 2019年に保険適用開始となった
修正型電気けいれん療法(mECT)
- 重症例や自死リスクが高い場合に適応される
- 全身麻酔下で安全を確保し実施される
これらの物理的治療法では、脳の特定部位に直接的な刺激を与えることで神経活動を調整し、症状の改善を図ります。
2025年現在で受けられる施設は限られていますが、近年の技術進歩により安全性も上がってきており、保険適用も拡大されている注目のアプローチ法といえるでしょう。
日常生活でできるセルフケア
生活の中で、うつ病の回復を助ける・または発症リスクを抑えるポイントもいくつか存在します。
休息する
とても難しいもののまず行わないといけないのはこの「休息」です。うつ病の改善には必須ですから、罪悪感を感じる必要はありません。人によっては学業を休んだり仕事から離れることも必要になるでしょうし、積極的に脳を休めるという意味ではデジタルデトックスをする(スマホやSNSと距離を置く)のも良いでしょう。
規則正しい生活を心がける
うつ病をはじめとした精神疾患で多くみられるのが不眠です。また不眠そのものがうつ病の発症、再発リスクあるいは重症リスクを高めるともいわれています。不眠があり、なかなか寝付けない・あるいは途中で覚醒してしまい眠れないといった睡眠の質の問題を抱えている場合には医師に相談しましょう。
睡眠から改善することが困難な場合は、朝の決まった時間に日光を浴び、食事を摂るなど、体内のリズムを一定に保つ意識を持つことから始めてみましょう。
適度な運動
適度な軽い負荷の運動(散歩や、少し息が上がる程度の簡単な運動など)をすると、実際に脳内のセロトニンの濃度が上がりストレス状態の改善がみられます。しかし自分のペースで行うことが大事ですから、無理に行う必要はありません。また、運動すればするほど良いというわけでもなく、高負荷の運動は逆にコルチゾルなどのストレスホルモンが増加すると言われています。できる範囲で、軽い運動を継続して行うようにしましょう。
まとめ
うつ病は「気の持ちよう」ではなく、適切な休息と治療が必要な病気です。
もし「うつ病かもしれない」と感じたら、一人で悩まずに精神科または心療内科で相談することをお勧めします。
また、相談室LITERASでは認知行動療法・行動活性化療法・睡眠衛生指導を受けることができます。
「うつ病かもしれず受診を迷っている」という方には、受診やセルフケアについての具体的なアドバイスとサポートも可能です。精神科病院等で臨床経験を積んだ公認心理師が対応しますのでご安心ください。
下記リンクから初回無料カウンセリングが受けられますので、ぜひお気軽にご相談ください。