「最近、家族の様子がおかしい」「自分の体験していることが統合失調症の症状なのだろうか」、そんな心配や疑問を抱えながら、この記事にたどり着いた方も多いのではないでしょうか。
統合失調症は当事者ご本人にとっても、またご家族にとっても大きな不安を招く疾患です。
今回は、統合失調症の概要や症状について幅広く解説していきます。原因・治療法まで幅広く取り上げているため、気になる方はぜひ参考にしてみてください。
統合失調症とは
統合失調症(とうごうしっちょうしょう)とは、脳の様々な働きをまとめることが困難になる精神疾患です。
考えや気持ちがまとまらなくなる状態が続き、幻覚や妄想、思考の混乱などの症状が現れます。
2002年までは「精神分裂病」と呼ばれていましたが、日本精神神経学会が名称を現在の「統合失調症」に変更しました。この名称により、思考や知覚・感情といった機能を「統合」する力を「失調」している状態、つまり適切にまとめることが出来なくなっているという病態生理を表現しています。
統合失調症の症状
統合失調症の症状は、「陽性症状」「陰性症状」「認知機能障害」と大きく3つのカテゴリーに分類されます。
すべての患者さんにすべての症状が現れるわけではないことを理解しておくことが重要です。
陽性症状
陽性症状とは、健康な状態では経験しない症状のことです。
幻覚
幻覚は、統合失調症において最も典型的な症状です。以下に例を挙げます。
統合失調症の中で圧倒的に多くみられる症状で、周囲の人には聞こえない声が聞こえる。
一般的には批判的・命令的な内容が聞こえてくる場合が多いため、本人も苦痛を感じていることが多いです。
他にも「いま電話でタクシーを呼びましたね」という実況中継のような声が聞こえる、複数人が会話する声が聞こえる、といった様々なパターンが見られます。
幻聴に反応して表情を変えること=「空笑(くうしょう)」
声に出して対話や返事をすること=「独語(どくご)」
これらもよく見られる症状です。
たとえば「皮膚に虫が這っている感じがする」「脳が燃えている感覚がある」など、
実際には起こっていない奇妙な身体感覚を感じることです。
実際には存在していないものの臭いを感じる症状。不快な臭いがきっかけで「毒を盛られている」といった新たな妄想へと発展することもあります。
妄想
妄想は幻覚と並んで最も典型的な症状の一つです。また、これらの妄想は周りが否定しても修正できないのが通常です。
現実には存在しない被害を信じること。妄想の中でも最も多いのがこの被害妄想とされています。
「周りの人たちが自分に対して嫌がらせをする」「ずっとつけまわされている・監視されている」「自分の存在が邪悪な集団から攻撃されている」「この会話も盗聴されている」など様々なケースが見られます。
自分が見聞きした情報を、なんでも自分に関連付ける症状。
例えばテレビやネットの情報を見て「自分に関する情報を流している」と感じたり、
通りすがりの人の何気ない行動を「自分への当てつけだ」と信じたりします。
自分のステータスや価値に対し、実際よりも高く感じて過大評価をする症状。
実際よりとても裕福であるとか、自分は世界を動かす力がある・あるいは特殊な才能を持っていて偉大な存在だと信じ込みます。
例えば「お腹の中に何かが入っている」「脳が溶けてしまっている」など、身体的な妄想を呈する症状です。
思考障害
思考にまとまりがなくなり、道筋・内容・形式に障害が見られます。
代表的な症状は、思考に一貫性がなく考えがあちこちに飛んでしまう「連合弛緩」。
思考を言葉に出すと、周囲の人にとって支離滅裂な内容の話に聞こえることが多い。
さらに症状が重くなると、まったく関連性のない単語だけが次々と出てくる「言葉のサラダ」という状態が生じることもあります。
自我障害
思考や行動について、他者ではなく自分が行っているという感覚が損なわれます。
「自分と他者」、「内的体験」と「現実」の境界が曖昧になることが特徴です。
- 自分の考えが周囲に漏れ伝わっているように感じる思考伝播
- 自分の考えが声になって聞こえる考想化声
- 自分の考えが他者に奪われる感覚=思考奪取、逆に他者の考えが自分の頭に入ってくる感覚=思考吹入
- 自分が誰かにコントロールされて行動しているように感じる作為体験
陰性症状
陰性症状は、健康時にあった機能が低下・消失する症状です。
感情の平板化ともいわれ、感情の起伏に乏しくなったり(喜怒哀楽をあまり感じなくなる)、それに伴い表情の変化もみられなくなったりします。
考えが出にくい(思考制止)あるいは完全に思考が止まってしまう(思考途絶)といった症状がみられます。
この場合も会話がぎこちなかったりあるいは急に止まったりするのが特徴。
- 以前楽しんでいた趣味に興味を示さない
- 何もせずにゴロゴロしている時間が増える
- 人との関わりを避けるようになる
- 外出を嫌がり、部屋に閉じこもる
- 会話が減り、コミュニケーションを取りたがらない
認知機能障害
認知機能障害は、日常生活や社会生活に大きな影響を与える症状です。
- テレビを最後まで見ることができない
- 新聞や本を読み続けることが困難
- 作業中に気が散りやすい
- 新しい情報を覚えにくい
- 約束や予定を忘れやすい
- 学習した内容を定着させることが困難
- 計画を立てて実行することが困難
- 問題解決能力が低下する
- 優先順位をつけることができない
- 情報を処理するのに時間がかかる
- 複数のことを同時に行うことが困難
- 反応が遅くなる
統合失調症の有病率・性差
研究によって小さい誤差がありますが、生涯有病率は概ね0.6~1.9%と言われています。
人口の約1%・つまり100人に1人の割合で発症する可能性があり、決して珍しい疾患ではありません。
性別によって統合失調症を発症しやすいといったような性差の報告はなく、
ほぼ男女ともに同等に発症するとされています(男性の方がやや多いとの報告もある)。
好発年齢は思春期から40歳頃までとなりますが、男女別で発症する時期には差がみられ、
男性は10代後半~20代前半の若年層で、女性は20代前半~20代半ばに好発します。
統合失調症の原因
統合失調症の正確な原因については現在も研究が続けられていますが、遺伝的要因と環境要因など複数の要因が複雑に関わり合って発症するというのが現代医療の考えのベースになっています。
家族歴による発症リスク
一般的な発症率は先述の通り1%。
しかし、第一度近親(親・兄弟姉妹・子)に患者がいる場合の発症率は約10-12%であり、一卵性双生児では約45%と確率が大幅に上がることが知られています。
一卵性双生児で45%というのは高い数字にもみえますが、
100%ではないということは逆に遺伝のみが原因ではない、という事実も示しているといえるでしょう。
脳の構造・機能の変化
脳の感情や記憶のバランスを図る「神経伝達物質」の異常やドパミン系の機能異常、また脳構造(前頭葉・側頭葉の体積減少、脳室の拡大など)の変化が挙げられます。
胎児期から思春期にかけての脳発達の問題も要因の一つとして考えられています。
妊娠・出産時のリスク
妊娠時の母体の感染症や、出産時の合併症(低出生体重・低酸素症など)も発症のリスク要因と言われています。
強いストレス
人生の重大な変化(進学、就職、結婚、離婚)、人間関係の深刻な問題(いじめや心的外傷)、経済的困窮、家族から受けた心理的トラウマ(身体的・心理的・性的虐待)などもリスク因子の一つです。
統合失調症の治療
統合失調症の治療は飛躍的に進歩しており、早期の・また適切な治療により症状の改善と社会復帰が期待できるようになりました。
薬物療法(生物学的治療)
統合失調症では、「ドーパミン仮説」といって、脳内のドーパミンという神経伝達物質のバランスが崩れることで症状が出現すると考えられています。ドーパミンが働きすぎても、逆に働きが弱すぎてもよくありません。
そのため、症状に応じて脳内のドーパミンを薬で調節するというのが基本的な治療の考え方です。
抗精神病薬
統合失調症治療の中核となる薬物です。
- 第1世代抗精神病薬(定型抗精神病薬)
ハロペリドール、クロルプロマジンなど
主にドーパミンD2受容体を強くブロックします(ドーパミンが働きにくくする)。陽性症状の治療として用いられることが多い。
- 第2世代抗精神病薬(非定型抗精神病薬)
リスペリドン、オランザピン、アリピプラゾールなど
ドーパミンとセロトニン受容体を調節します(第1世代と比べて適度にブロックするため、一部のドーパミンは働ける状態)。第一世代と比較して副作用が少ないと言われており、陰性症状にも効果を発揮しやすい。
- 長時間作用型注射薬(LAI)
抗精神病薬を筋肉注射で投与する方法。薬が徐々に血中に放出されるため、2週間~3ヶ月効果が持続します。
投薬と異なり、飲み忘れを予防できるというのがメリット。
毎日薬を飲むのが大変、あるいは実際に自己中断して再発を繰り返してしまうといった方や服薬管理が難しいという方に、向いている方法といえるでしょう。
統合失調症の治療で問題となるのが服薬を自己中断してしまうことがあるという点です。
症状が改善してくると「薬はもう必要ない」と自己判断して服薬を中断してしまい、再発するケースが増えてしまいがちですが、再発を繰り返すほど予後は悪化するといわれています。
そのため、症状が改善しても主治医の指示がある限りは服薬を継続し、減薬等については主治医とよく相談したうえで慎重に決めることが重要です。
その他、症状に応じて抗うつ薬・抗不安薬・気分安定薬・睡眠導入剤なども用いられることがあります。統合失調症では特にうつ症状を併発することが多いため、陰性症状の改善という意味合いでも使用されることがあるでしょう。
また、女性は治療薬に対する反応が男性よりも良いとされています。しかし治療に対する反応の差についてのメカニズムなどはまだはっきり解明されていません(女性ホルモンのエストロゲンは抗精神病薬の血漿濃度を直接上昇させる効果があるからという説もあります)。
心理療法/リハビリテーション
陽性症状の改善、再発防止、社会機能の維持に対する効果が確認されています。
認知行動療法の目的は、症状を「完全に消す」のではなく「上手に付き合う」ということ。
幻聴や妄想に対して、「本当に現実のものなのか」という洞察を行い、幻聴以外の情報に注意を向けるようにしたり、段階的に妄想の真偽を確かめたりなど「症状に適切に対処するスキル」を学んでいきます (Jauhar et al.,2014; Turner et al.,2020)。
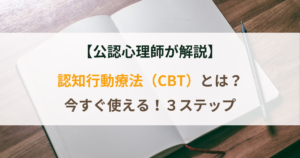
集団療法として実施されることが多く、認知行動療法よりも導入しやすい治療法。
メタ認知トレーニングでは、妄想の症状によって形成された確信や信念を俯瞰します。
「どうしてそう確信したのか?」「その認識は誤っていないか?」と自ら意識し気づくことで、妄想の強度・確信を和らげる効果が確認されています (Eisner et al., 2018)。
患者さんのご家族に対して症状・治療の説明や情報提供、心理的サポートを行います。
英国の治療ガイドラインでは最も推奨されており、家族介入によって再発率が40%近く低下することや、入院日数の減少、服薬アドヒアランスの向上といった効果も確認されています (Pharoah et al., 2010)。
対人関係や日常生活に必要な社会技能を体系的に訓練する治療法。
行動療法の一種で、「練習によって上達する」という考え方です。
- 日常生活技能(買い物、料理、掃除など)
- 対人関係技能(会話、友人関係など)
- 職業技能(面接、職場での協働など)
- 疾病管理技能(症状管理、服薬管理など)
精神科リハビリテーションとしての作業療法、運動療法、音楽療法など、楽しみながらリハビリを行う中で、小さな「できた」を積み重ねることも重要です。脳と心を同時に回復させるアプローチ方法といえるでしょう。
まとめ
統合失調症はご本人や家族にとって不安を招く疾患ですが、現代の医学により多くの患者さんが回復し、社会復帰を果たしています。
症状に気づいたら一人で悩まず、専門機関に相談することから始めましょう。
相談室LITERASのオンラインカウンセリングは、認知行動療法やご家族へのサポートにも対応しております。
精神科病院で臨床経験を積んだ公認心理師がお話をうかがい、臨床心理学・精神医学のエビデンスに基づいて具体的なアドバイスをさせていただきます。
初回カウンセリングは無料ですので、お困りの方はぜひお気軽にご相談ください。

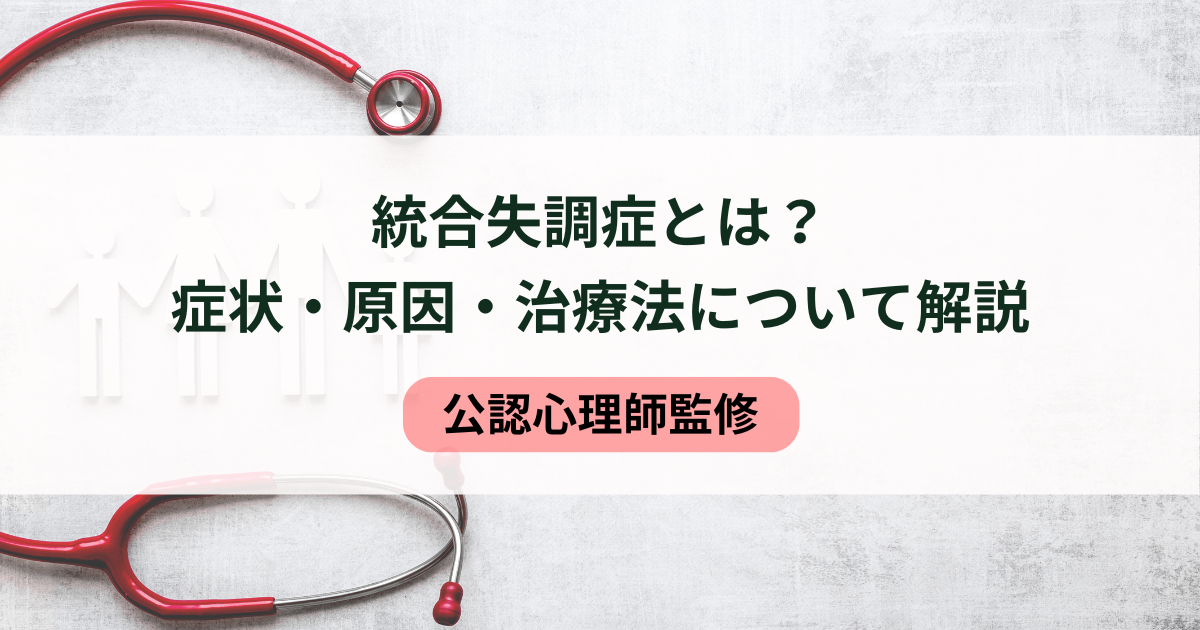
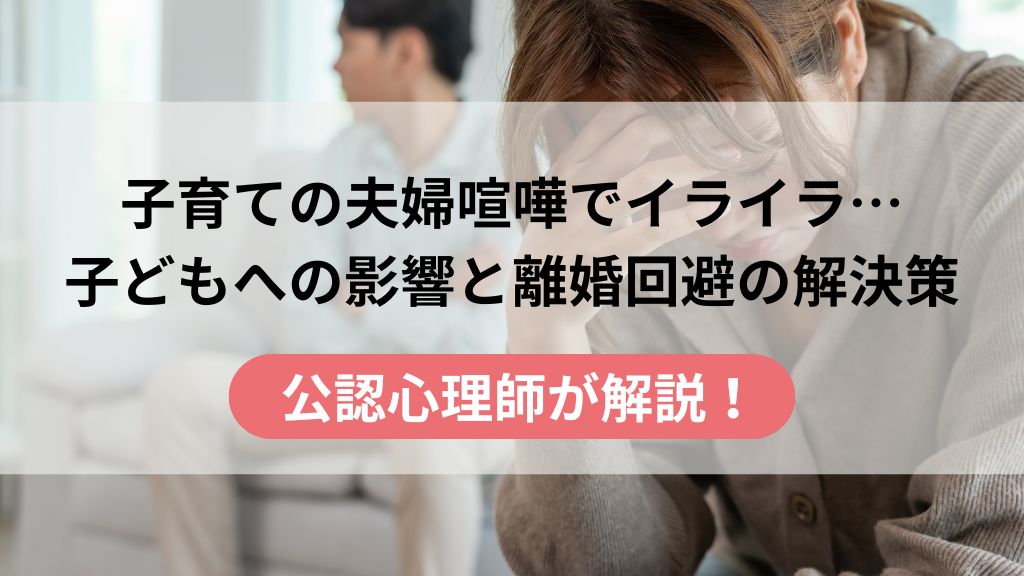
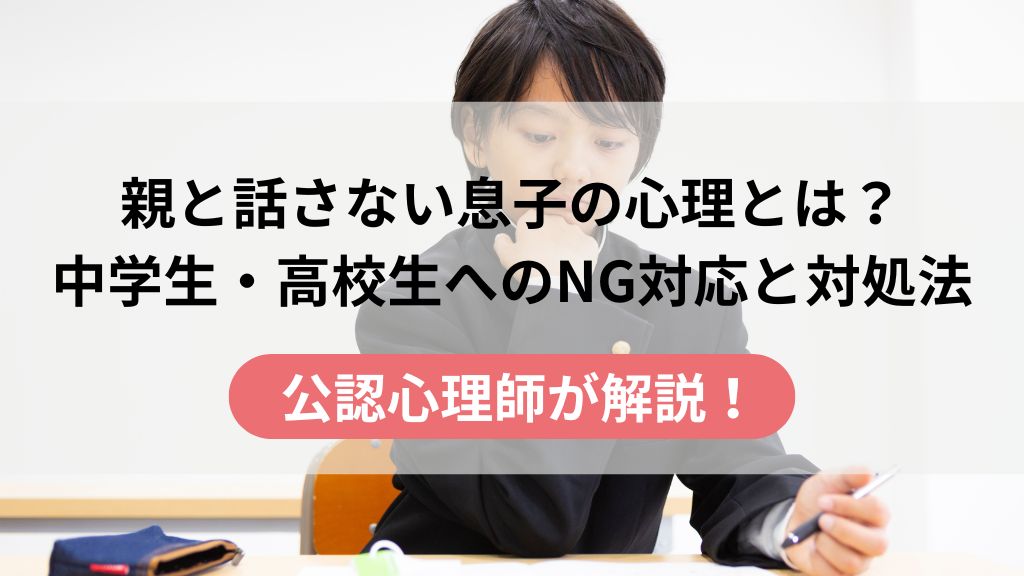
.jpg)