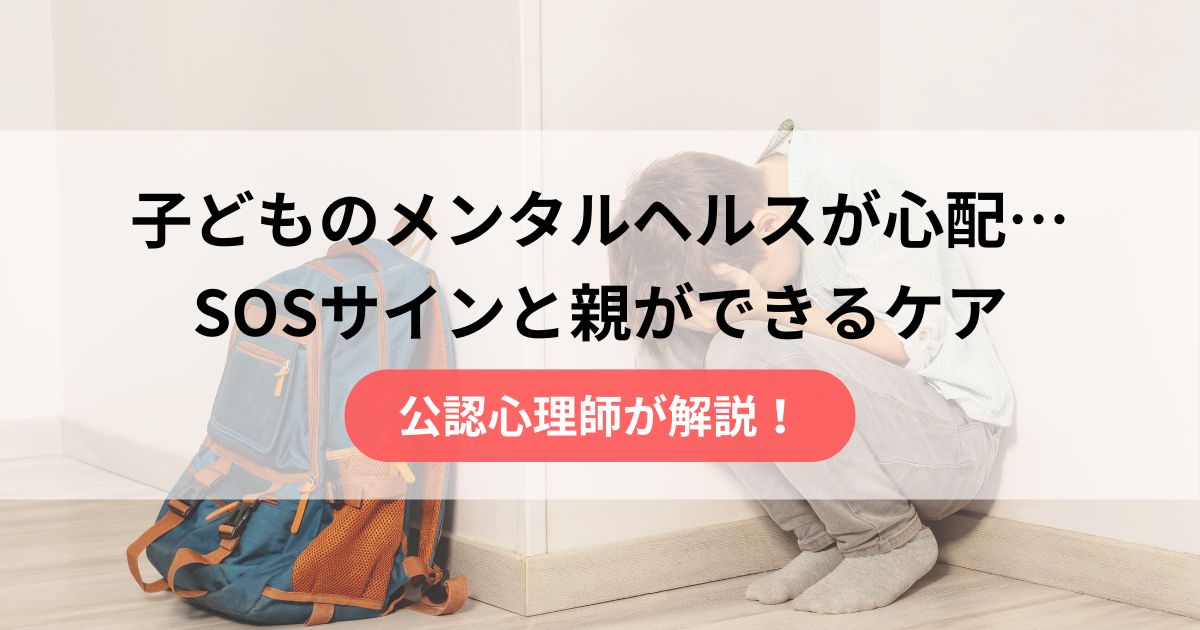「うちの子、最近なんだか様子がおかしいけれど、大丈夫だろうか…」
子どもの生活リズムの乱れや気分の落ち込み、学校への行き渋りといった変化に気づき、不安や心配を抱えていませんか。
子どもの状態が気になるのは、保護者としてごく自然なこと。
子どものメンタルヘルスは大人と異なる特徴もあり、一見すると気づきにくいことがあります。
この記事では、子どもが発しているかもしれない「こころのSOSサイン」を具体的に解説します。
家庭ですぐにできる関わり方や、悩みに合わせた相談先について一緒に考えていきましょう。
子どものメンタル不調でみられる3つのSOSサイン
大人のメンタル不調とは異なり、子どもは「抑うつ」よりも「イライラ」が前面に出やすいなど、あらわれ方に特徴があります。まずは、家庭で気づきやすい3つのSOSサインをみていきましょう。
①生活リズムの乱れ(睡眠・食事)
こころのエネルギーが低下してくると、当たり前にできていた生活習慣の維持が難しくなりがちです。
- 朝、時間になっても起きられない
- 夜になかなか寝付けない、または夜中に何度も目が覚める
- 食欲がない、あるいは逆に食べ過ぎてしまう
- お風呂に入るのを面倒くさがる
生活リズムの乱れは、本人の「怠け」や「わがまま」ではなく、こころが休息を必要としているサインなのかもしれません。
②身体の不調の訴え(頭痛・腹痛)
子どもはこころのつらさをうまく言葉で表現できず、身体の症状としてあらわすことが少なくありません。
たとえば、次のような状況が挙げられます。
- 登校時間が近づくと、決まって頭痛や腹痛を訴える
- 病院で検査をしても、とくに異常が見つからない
- 休日や好きなことをしているときには、症状がやわらぐ
以上のような不調は、学校など特定の状況に対する強いストレスや不安が背景にある可能性があります。
③感情や行動の変化(無気力・イライラ)
感情や行動に変化がみられるのも、注意深く見守りたいサインの一つです。
- 好きだったゲームや趣味に興味を示さなくなった
- 口数が減り、自分の部屋にこもりがちになった
- ささいなことで怒りっぽくなったり、反抗的な態度が目立ったりする
以上のような変化は、内面で抱える苦痛や不安から自分を守る反応であることも少なくありません。
怒りっぽくなる・イライラするなどの反抗的にみえる態度も、実は助けを求める気持ちが隠れている可能性があります。
なぜ?子どものこころが不安定になる3つの背景
子どもが不調になる背景にはなにがあるのでしょうか。
子どものこころが不安定になりやすい背景を「学校」「家庭」「特性」の3つの視点から解説します。
①学校生活でのストレス
一日の大半を過ごす学校は、子どもにとって成長の場であると同時に、ストレスの原因ともなり得ます。
主な学校生活上のストレスは以下のとおりです。
| ストレス要因 | 具体例 |
|---|---|
| 友人関係 | ・友達に仲間外れにされた、無視された ・自分の性格や行動について、悪口を言われた |
| 教師との関係 | ・授業中にわからない問題で当てられた ・理由を聞いてもらえないまま注意された |
| 学業のプレッシャー | ・テストの成績が悪かった ・授業の内容がよくわからなかった |
以上のようなストレスを抱えていないか、日頃の会話からチェックしてみましょう。
②家庭や社会環境の変化
学校だけでなく、家庭や現代社会特有の環境も、子どものこころに深く関係しています。
家庭では、夫婦間の対立や親からの期待などの緊張した雰囲気は、子どもを不安にさせることがあります。
家庭が安心できる場所だと感じられないと、こころのエネルギーを回復させることが難しくなるでしょう。
また、SNS上の人間関係もストレス要因の一つです。
友人の投稿と自分を比較して落ち込んだり、ネットいじめにあったりするなど、デジタル上のストレスも無視できません。
③生まれ持った繊細さと特性
子どもの中には、周りの環境からのストレスを強く感じやすい気質を持つ子がいます。
「Highly Sensitive Child(HSC)」と呼ばれ、生まれ持った特性の一つです。
HSCのお子さんには、たとえば次のような特徴がみられることがあります。
- 人の気持ちにとても敏感で疲れてしまう
- 大きな音や強い光、人混みなどが苦手
- 物事によく気がつき、深く考えて行動する
- 直感が鋭く、創造性が豊か
以上のような特徴から、クラスなどの集団場面が刺激的で疲れてしまうことが多いでしょう。
図書室や保健室などの一人で落ち着いて過ごせる居場所があったとしても、ストレスの感じやすさは高くなりがちです。
子どものSOSに気づいたら?親がすぐできるメンタルケア
SOSサインに気づいたら、保護者としてなにができるでしょうか。家庭での関わり方を3つ紹介します。
①まずは気持ちを受け止める
子どもが不調を訴えたり学校に行きたくないと話したりしたとき、感情を否定せずにありのまま受け止めることが大切です。
原因を追及したり、「頑張って」と励ましたりすることは、子どもを追い詰めてしまう可能性があります。
たとえば、次のように声かけをしてみましょう。
- 「学校に行きたくないんだね」
- 「朝、起きるのがしんどいんだね」
- 「嫌なことがあったんだね」
- 「話してくれてありがとう。そう感じていたんだね」
判断や評価をせずに耳を傾けることで、子どもは「気持ちをわかってもらえた」と安心しやすくなります。
②心と身体を休ませる
こころのエネルギーが不足しているときは、なによりも休息が必要です。
家庭が「なにもしなくても、そのままでいていい場所」になることが、回復への第一歩となります。
たとえ、ゲームやスマートフォンに没頭していたとしても、今はかろうじてこころのバランスを保っている状態かもしれません。「怠けている」と捉えず、「必要な休息」と考えて、無理のない範囲で見守ってあげましょう。
③親だけで抱えず相談する
子どもの問題に直面したとき、親が「自分のせいで…」と一人で抱え込んでしまうことは、珍しいことではありません。しかし、一人で悩み続けることは、ご自身の健康を損なうだけでなく、家庭内の雰囲気をさらに悪化させてしまう可能性があります。
親自身の不安や焦りを話せる場所を見つけることが、結果としてお子さんへの適切な関わりにつながります。
まずは親だけでも専門家に相談してみる、という選択肢があることを知っておいてください。
悩みに合わせた相談先の選び方
状況に応じて適切なサポートが受けられるよう、相談先にはいくつかの選択肢があります。それぞれの特徴を理解し、状況に合わせて選ぶことが大切です。
| 相談先 | 相談内容の例 | 相談シーンや特徴 |
|---|---|---|
| 学校の相談窓口 (スクールカウンセラーなど) | 友人関係、いじめ、学習面の悩みなど | 学校生活での問題が中心のとき ・無料で相談できる ・担任教師などと連携しやすい |
| 医療機関 (児童精神科・心療内科など) | 気分の落ち込み、強い不安、不眠など | 専門的な診断・治療が必要なとき ・子どもの精神疾患を専門に診断 ・薬物療法を含めた治療が可能 |
| 公的な相談機関 (児童相談所・教育センターなど) | 発達の悩み、不登校、養育困難など | 福祉的なサポートが必要なとき ・無料で相談できる ・学習支援を受けられる |
| 民間のカウンセリングサービス | 医療機関の受診を迷っている、 親の関わり方を知りたい など | 気軽に専門家の助言を得たいとき ・オンラインなら柔軟に相談できる ・夜間や休日に対応している場合がある |
どの窓口に相談すればよいか迷うこと自体も、自然なことです。
一つの窓口に相談してみて、別の場所を紹介してもらうことも可能ですので、まずは外部のサポートを頼ることを考えてみましょう。
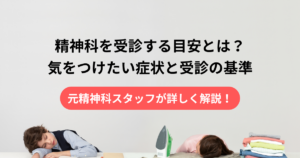
子どものメンタル不調はまず相談してみましょう
お子さんのメンタルヘルスの不調は、生活リズムの乱れや身体の不調、感情や行動の変化といった、さまざまなSOSサインとしてあらわれます。
お子さんのSOSに気づいたとき、まず大切なのは、つらい気持ちを否定せずに受け止め、安心できる休息の場を確保してあげることです。そして、一人で問題を抱え込まず、学校や医療機関、カウンセリングなど、適切な外部のサポートに頼ることをためらわないでください。
「子どもの様子が心配だけれど、病院に連れて行くべきか迷う…」
「専門医の予約が数か月待ちで、それまでなにもしないままでいるのが不安…」
「まずは、親としてどう関わればいいのか、具体的なアドバイスがほしい」
もしこのような思いを抱えているのなら、オンラインカウンセリングで専門家に相談してみるのも一つ。
相談室LITERASでは、精神科受診の必要性やお子さんとの関わり方、生活習慣の整え方などについて、医療機関で臨床経験を積んだプロの心理師から具体的なアドバイスを得ることができます。
もし悩んだときは、初回無料カウンセリングでまずはお気軽にご相談ください。