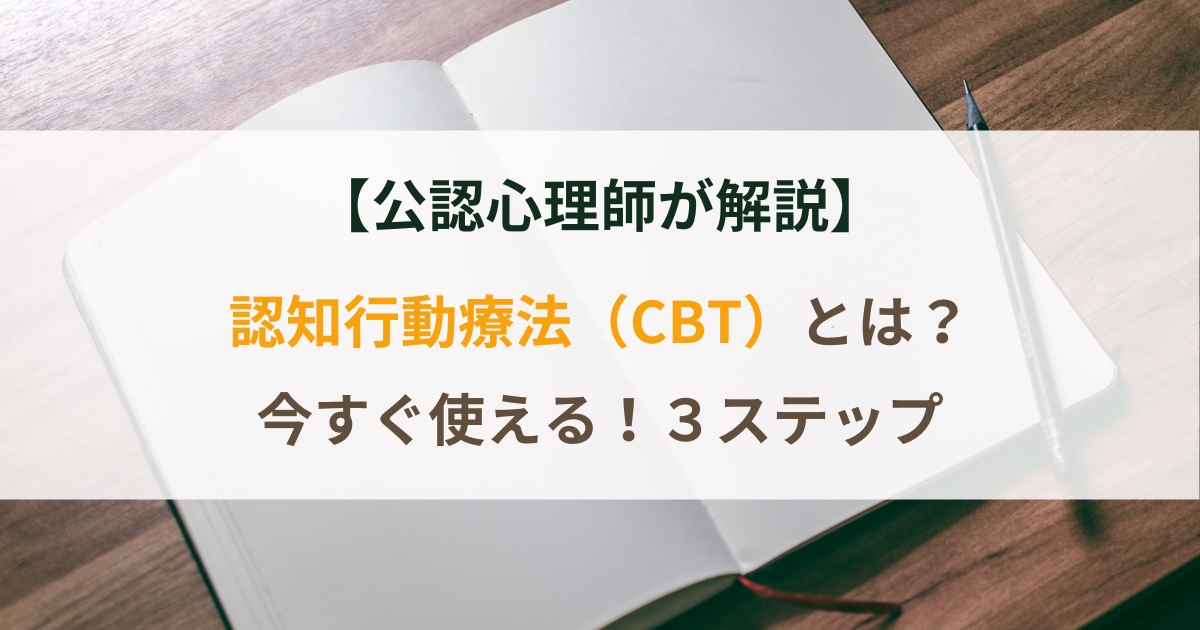認知行動療法(CBT)とは、考え方や行動に焦点を当てた心理療法の一種です。
近年はセルフヘルプ本も多く出版されており、ご存知の方も多いのではないでしょうか?
この記事では「認知行動療法について詳しく知りたい」という方に向けて、
精神科病院で臨床経験を積んだ公認心理師が、認知行動療法の概要や活用方法についてわかりやすく解説します。
認知行動療法とは?
はじめに、認知行動療法(Cognitive behavioral therapy: CBT)とは
私たちの「思考(考え方)、感情(気持ち)、行動が互いに影響し合う」という原則に基づいたアプローチです。

難しいわね。そもそも思考と感情ってどう違うの?
私たちは普段、思考と感情を分けてとらえることがないのでわかりにくいですよね。
では、次の例について想像してみてください。
Aさんは 友人から誕生日プレゼントをもらって 嬉しかった
このときの「嬉しかった」は感情(気持ち)。では、どうしてAさんは嬉しかったのでしょう?
「友人が自分の誕生日を覚えてくれていたんだ」 と思ったから
「友人が自分のことを思って選んでくれたんだ」 と思ったから
「ずっと欲しかったものを覚えていてくれたんだ」 と思ったから
これらは全てAさんの「思考(考え方)」。
「嬉しい」という感情一つとっても、その背景には様々な思考(考え方)があるのです。
そして、Aさんは友人にお礼を言ってプレゼントを受け取り、大切に持ち帰ったかもしれません(行動)。
では、もしAさんが全く異なる「思考(考え方)」をしていたらどうでしょう?
せっかくのプレゼントだけど既に持ってる物だ。
私の誕生日は3ヶ月も先なんだけどな。
→ すると、「嬉しい」ではなく「戸惑い」「残念」「悲しい」など別の感情が出てきたかもしれません。
そして、友人に気を遣って笑顔をつくり、嬉しそうなふりをするかもしれません(行動)。
このように 思考(考え方)・感情(気持ち)・行動は異なるものでありながら、互いに影響し合っているのです。
認知行動療法では、現在の悪循環を生み出している思考や行動のパターンを見つけます。
そして、思考や行動のレパートリーを増やし、出来事に柔軟に対処できる力を身につけていきます。
単に「ポジティブな考え方に変えればいい」のではありません。
自分の中にはなかった新しい思考・行動のパターンを模索し実践していく中で、
少しずつ柔軟な考え方や対処行動が取れるようになり、自然と気持ちが楽になるイメージです。
ちなみに、認知行動療法が有効であるとされる代表的な疾患には以下のものが挙げられます。
- 不安障害
- うつ病
- パニック障害
- 強迫性障害(OCD)
- PTSD(心的外傷後ストレス障害)
- 不眠症
他にも依存症、発達障害、摂食障害の治療や、ペアレントトレーニング、家族支援としての有効性なども確認されています。
認知行動療法を日常生活で使うための3ステップ
認知行動療法(CBT)の技法を日常に取り入れることで、メンタルヘルスを良好に保ちやすくなります。
以下に、自分でできる簡単なやり方を3ステップとしてご紹介します。
記録を使って整理する
まず、自分の気持ちや思考を客観的に分析するための記録をつけてみます。
- 出来事を記録する: いつ/誰が/どこで/何をしたかを記録(例: 昨日上司が職場で私のミスを指摘した)
- 感情を記録: そのときの感情(例: 悲しみ、不安、苛立ち)
- 思考を記録: 頭に浮かんだ考え(例: 「自分はダメだ」「また同じミスをして怒られるかもしれない」)
- 行動を記録: その後にとった行動(例: トイレにこもって泣いた)
これにより、出来事を客観的に振り返りながら、思考と感情のつながりを確認できます。

出来事をありのままに振り返ることって少ないし、
実際よりも悲観的にとらえてしまうことが多いかも。

そうですね。あらためて冷静に振り返ってみると
それほど悲観的な状況ではなかった、なんてことも。
そのギャップに自分で気づけることは大きな一歩です。
自動思考を認識する
思考(考え方)はたいてい出来事に対して突発的に浮かんでくるものなので、
認知行動療法では思考(考え方)のことを「自動思考」と呼んだりします。
突発的に浮かんでくる自動思考は、私たちにとってはまるで呼吸のように無意識的な反応。
育ってきた環境・性格・人間関係など様々な要因によって作り上げられていきます。
ですから、全く同じ出来事を経験をしても、人によって思い浮かぶ自動思考は異なります。
もし自動思考のパターンが事実とは異なる思い込みを含んでいたり、極端なほど楽観的・悲観的であれば、
それを「認知の歪み」と呼んだりします。認知の歪みはたいてい、感情や行動にも悪影響を及ぼします。
例:
- 出来事: 「昨日上司が職場で私のミスを指摘した」
- 自動思考: 「上司は私のことを嫌っているに違いない」
- 感情: 不安、恐怖
- 行動: 上司との接触を避ける
必ずしも自動思考が全て悪いとか、歪んでいるのではありませんが
まずは自動思考を意識して過ごし、自分の考え方の癖やパターンを知ることが第一歩!
別の思考パターンを挙げてみる
はじめの自動思考とは違う、他の考え方はできないかアイデアを出してみましょう。
例えば:
- 自動思考: 「上司は私を嫌っているに違いない」
- 別の思考: 「ミスを指摘されただけ。改善すればきっと大丈夫」
「上司だっていつも怒るわけじゃないし、他の人にも平等に指導してる」
できるだけ多く新しい思考のパターンを見つける中で「認知の歪み」を修正し、より現実的で建設的な視点を養います。
認知行動療法を使ったストレスマネジメント方法3選
認知行動療法(CBT)を応用したストレスマネジメントの方法をいくつか紹介します。
深呼吸とマインドフルネス
ストレスを感じたときには、呼吸法とマインドフルネスを組み合わせた練習が効果的です。
- 深呼吸: ゆっくりと4秒吸い、6秒吐く。
- 現在に集中: 今この瞬間に注意を向ける(音、匂い、感覚など)。
これにより、心拍数が落ち着き、ストレス軽減効果が期待できます。
心地良い活動のレパートリーを増やす
ストレス解消には、心地良い活動のレパートリーを増やすことも重要です。たとえば:
- 短い散歩: 家の中で悶々としてしまうときは外に出て体を動かしてみる
- 人と話す: 自分だけで抱え込ます人に相談したり、雑談するだけでも気が紛れる
- 作業に没頭する: ひたすら絵を描く、手芸をする、家事をする など余計なことを考えない時間を作る。
- リラクゼーション: ヨガや瞑想を取り入れる。
なるべくたくさんの行動パターンを試す中で、自分にぴったりのセルフケア方法を見つけます。
一人でじっと抱え込む状況を脱して行動することで、少しずつ変化を作り出すことが重要です。
スケジュール管理
スケジュールの詰め込みを避け、ストレスが過剰にならないようコントロールします。
作業を細分化して優先順位をつけて必要なタスクだけに集中したり、
ときには周囲の力を借りて自分の負担を軽くすることも必要かもしれません。
日記をつけてスケジュールを可視化するのもいいですね!
当たり前のように見えて、ストレスを管理するには様々なスキルが必要です。
周囲の人に上手に頼ったり時間管理のスキルを身につけることも、認知行動療法の技法に含まれます。
認知行動療法のおすすめの本
まとめ
認知行動療法(CBT)は、日常生活においても簡単に取り入れられる効果的な心理療法です。
この記事で紹介した技法を活用することで、ストレス管理や感情の安定に繋がります。
病院やカウンセリングルームでの対面カウンセリングはもちろん有効ですが、より気軽に相談したい場合はオンラインで受ける認知行動療法も有効とされています。
認知行動療法(CBT)についてより詳しく知りたい方や、専門家に気軽に質問してみたいという方、
「最近うつっぽくて精神科受診を迷っている」「自分で気分をコントロールできるようになりたい」
という方は、ぜひ 相談室LITERASのオンラインカウンセリングサービスをご利用ください。
当相談室では公認心理師が認知行動療法や精神科受診に関するご相談、家族相談を承ります。
エビデンスに基づいた情報提供を行っていますので、ぜひお気軽にご相談ください。